株式会社SHISEILABO 代表取締役兼CMOの武山です。今回は、世の中の仕組み、ビジネスの仕組みを数値で把握する方法として、相関関係の重要性について触れてみたいと思います。ビジネスの意思決定において「感覚」や「経験」は重要ですが、それを裏付ける数値的根拠がなければ、再現性のある成果にはつながりません。そこで鍵となるのが相関関係の理解と活用です。
相関係数・相関関係とは?
相関関係とは、2つのデータがどの程度一緒に動くかを示す関係性のことです。例えば、広告費が増えると売上も増える場合、「広告費と売上には正の相関関係がある。」という言い方をします。
相関関係を数値的に把握するために重要なのが、相関係数です。相関係数とは、相関関係の強さを-1(マイナス1)からプラス1の数値で表したもので、1は完全な正の相関(片方が上がればもう片方も必ず上がる)、0は相関なし、つまり関係性が見られない、-1は完全な負の相関(片方が上がればもう片方は必ず下がる)を表します。
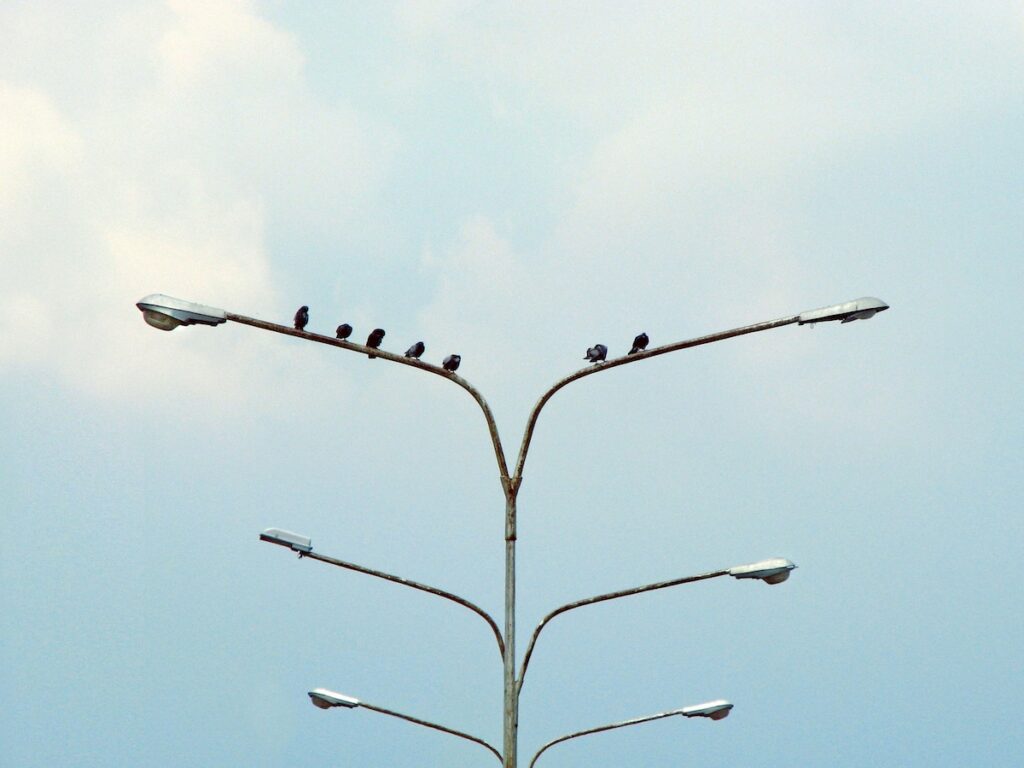
マクロの視点では株式トレードも相関係数がゴール
私は日本株を扱っていますが、金融市場では、相関関係の把握は必須です。例えば株式トレードでは、株価と為替レート、特定業種の株価同士、金利や原油価格と株価などこれらの間に強い相関関係があるかを見つけることが、リスク分散や利益獲得の戦略を立てる第一歩となります。マクロ分析の世界では「相関係数を見つけること」自体が重要なゴールのひとつです。
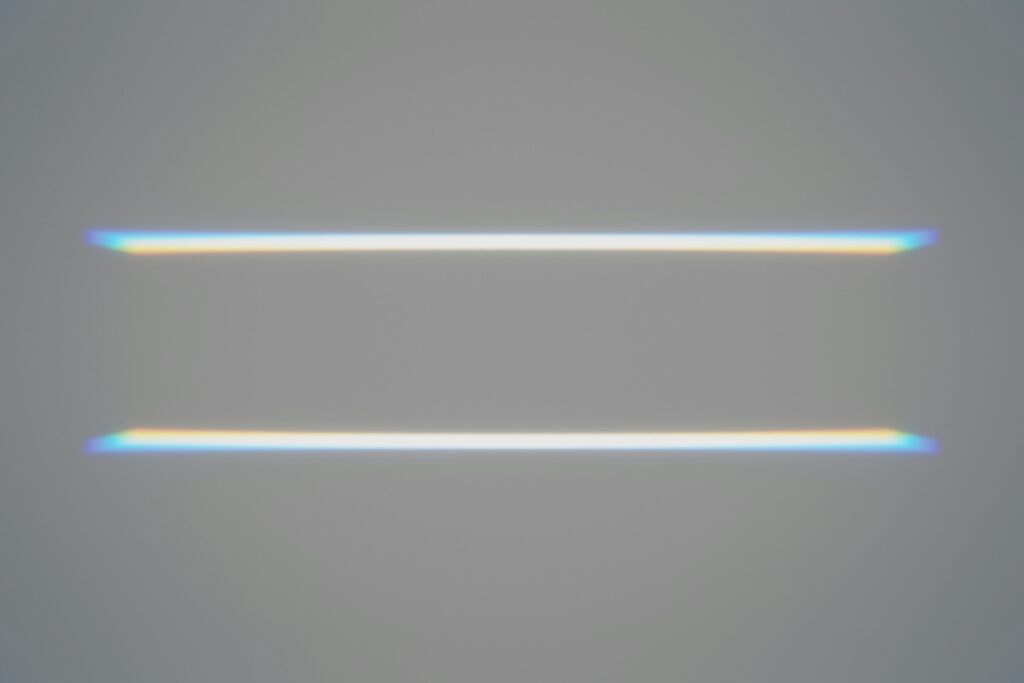
売上や契約件数と相関関係にあるものを見つけるステップ
SHISEILABOの支援
SHISEILABOがクライアント支援で行う一般的なフローをお伝えします。
- 目的変数の設定
売上、契約件数、リピート率など、最終的に伸ばしたい指標を決めます。 - 説明変数の抽出
広告費、来店数、Webアクセス数、SNSフォロワー数、メール開封率など、影響を与えそうな要素をリスト化します。 - 一定期間のデータ収集
最低でも3〜6ヶ月、理想は1年以上の時系列データを用意します。 - 相関分析
ExcelやBIツールで相関係数を算出し、強い関係性を持つ項目を特定します。 - 仮説と検証
強い相関が因果関係かどうかを、実験や施策で確かめます。新たなタッチポイントを増やして、説明変数を常に探索する流れです。

相関係数の活用には一定期間のデータ集計が必要
注意点として、相関係数は短期的なデータではブレが大きく、誤った判断を招くことがあります。例えば、1週間の売上と広告費の動きを見ても、偶然の要因や外部イベントで数字が変動する可能性が高いです。
最低でも数ヶ月単位でデータを蓄積し、季節性やトレンドの影響を取り除くことで、信頼できる相関関係が見えてきます。
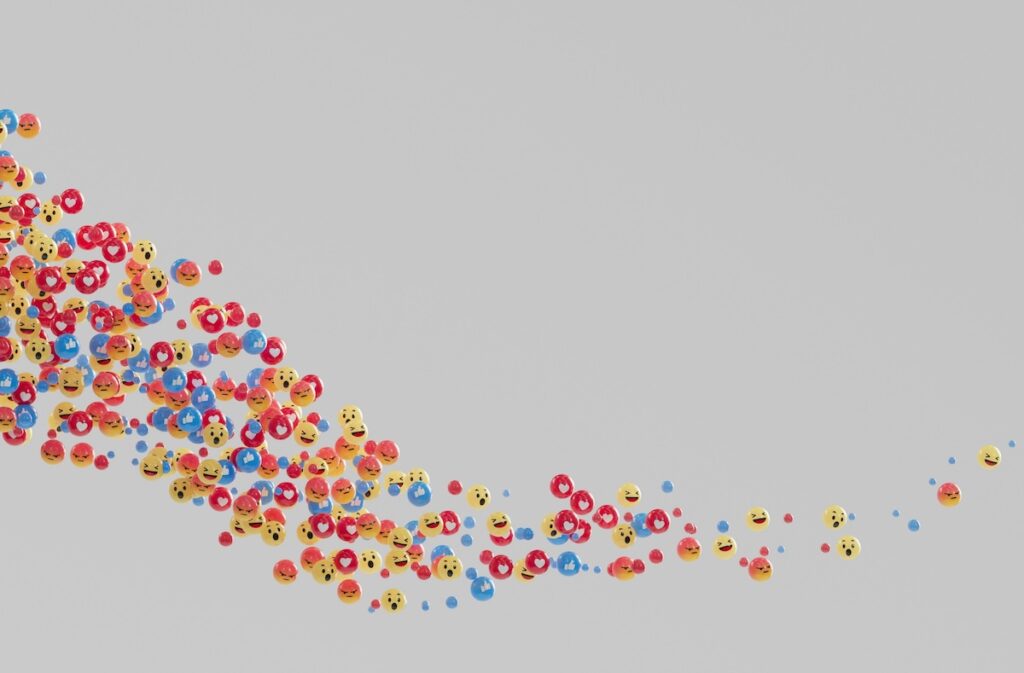
相関係数を活用したマーケティング戦略とは?
SHISEILABOでは、相関分析をマーケティング戦略の起点として、「何を伸ばせば売上や利益や成約が伸びるか」を明確にし、その結果を広告・営業・商品企画に反映しています。マーケティング戦略で相関係数を用いる場合の基本的なルールをお伝えします。
- 効果の高い施策の特定
売上と強く相関する施策(例:特定媒体の広告費、SNS投稿数)にリソースを集中投下する。 - KPI設計の精度向上
直接売上に結びつかない中間指標(例:メルマガ開封率)でも、強い相関があればKPIに採用する。 - 予測モデルの構築
相関係数をもとに、将来の売上や契約件数を予測する数理モデルを作成する。
まとめ
相関関係を数値で把握することは、ビジネスを「感覚」から「戦略」へと進化させるための武器です。
相関関係は、世の中の仕組みを理解する手助けとなり、自社のビジネス構造を可視化することにつながります。また、成果に直結するアクションを明確化して、営業プロセスのPDCAサイクルに新たな文化を育むことでしょう。
これらを実現するために、まずはデータを集め、相関係数で関係性を可視化する習慣を持つことから始めてみてください。データをもっと活用しましょう!
