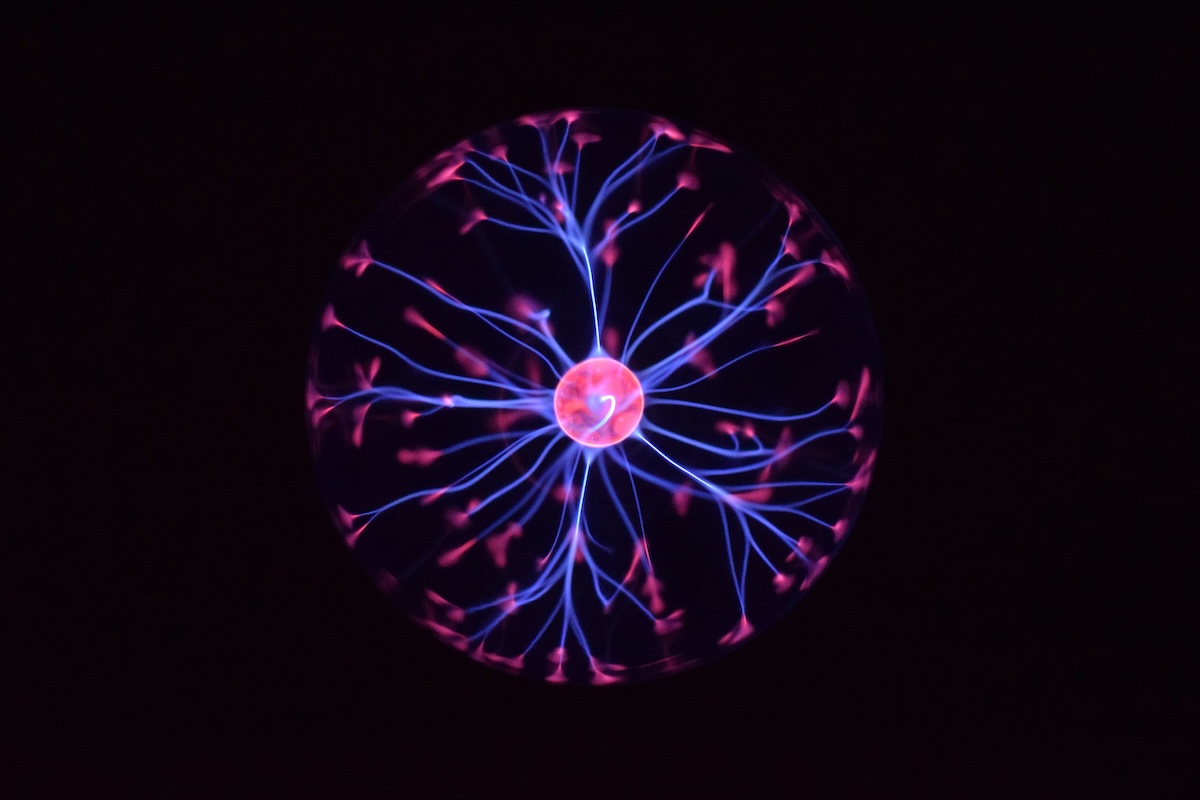私たちは毎日、無数の情報に触れながら暮らしています。無数の情報は、無意識的に脳にインプットされるものもあれば、意識的に脳にインプットする情報もあります。それらの情報を理解し、判断し、行動に移すための土台となるのが「認知」です。認知とは、知覚・記憶・思考・学習などを含む、心の働きの総称です。
認知には「知覚」「注意」「記憶」「言語」「思考」「メタ認知」など多様な種類があります。これらは単独で働くのではなく、互いに影響し合いながら私たちの行動や学習を支えています。
日常生活や教育、ビジネスで成果を高めるには、「自分はいまどの認知を使っているか」を意識することが効果的です。特にメタ認知を活用することで、自分の思考を客観的に見直し、次の行動をより良い方向に導くことができます。今回は「認知の種類」を整理しながら、私たちの思考や行動を支える仕組みを見ていきましょう。
知覚認知
目や耳など五感を使って外の世界を理解するはたらき
知覚認知とは、五感を通して外界を把握する働きです。五感は、目で見る視覚的な感覚、耳で聞く(聴く)聴覚的な感覚、手や足など身体で触る触覚的な感覚、鼻を使った嗅覚的な感覚、舌で感じる味覚的な感覚の5つがあります。
例えば、リンゴをリンゴだと、認知するプロセスは、5感により異なります。赤いリンゴを見て「リンゴだ」とわかる場合も、リンゴの香りから「リンゴだ」とわかる場合もあります。手で触って、梨ではなく、「リンゴだ」とわかる人もいるでしょう。
また、音で危険を察知するというのも立派な五感の働きです。
近く認知は、「日常の安全や学習の基盤となる認知。」ということができそうです。
注意認知
たくさんの情報の中から大事なものに集中する力
注意認知とは、膨大な情報の中から必要なものに焦点を当てる機能です。例えば、教室で先生の声に集中するというのは注意認知です。また、運転中に道路標識に注意するというのも注意認知にあたります。
注意認知は、集中力や効率的な行動に直結します。
注意認知で有名な概念として、カクテルパーティー効果があります。カクテルパーティー効果とは、100人や200人の大人数がいる比較的広い会場でも、自分自身に関連するキーワードを聞き取ることができる人間の特別な認知効果。例えば、私の名前が「五十嵐」で出身地が「沖縄」、「サザンオールスターズ」に興味がある場合に、遠くで誰かが、「五十嵐」「沖縄」「サザン」と発言した言葉を、それ以外の雑音を無視して聞き取ることができるというものです。私は、その誰かに興味を持つことでしょう。
記憶認知
覚えたことをしまっておき必要なときに取り出す力
記憶認知とは、情報を蓄えて必要なときに取り出す仕組みです。一般的に、短期記憶(数秒〜数分)、長期記憶(長期間保持)という2つの記憶概念が存在します。記憶認知は、学習や経験の活用に欠かせない認知です。
言語認知
言葉を理解して使う力
言語認知とは、言葉を理解し、使う能力です。言葉を理解して使う力で、読む・書く・話す・考えるのすべてに関係します。読み書きや会話だけでなく、思考そのものにも直結します。例えば、本屋文章を読んで意味を理解する、概念を整理して説明するなどが言語認知にあたります。
言語認知は、社会生活やビジネスでのコミュニケーションの中核となります。特に、LINEやGoogle ChatやSlackなどのメッセージツールを多用する現代人に欠かせない認知です。
思考認知
情報を組み合わせて考えたり問題を解いたりする力
思考認知とは、情報を組み合わせて判断・推論・問題解決を行う機能です。例えば、数学の問題を解く、企画を立てるなどが思考認知にあたります。創造性や意思決定に不可欠な認知ですが、生成AIはこの思考認知を代替する手段です。
メタ認知
自分の考えや勉強のやり方を客観的にふり返る力
メタ認知とは、「自分の認知を認知する」ことです。つまり、自分の考え方や理解の状態を客観的に把握する力がメタ認知です。
例えば、試験勉強で「この分野はまだ理解が浅い」と気づくこと。そして、学習方法を変えるという行動を促すことは立派なメタ認知にあたります。自己成長や学習効率を高めるカギがメタ認知です。
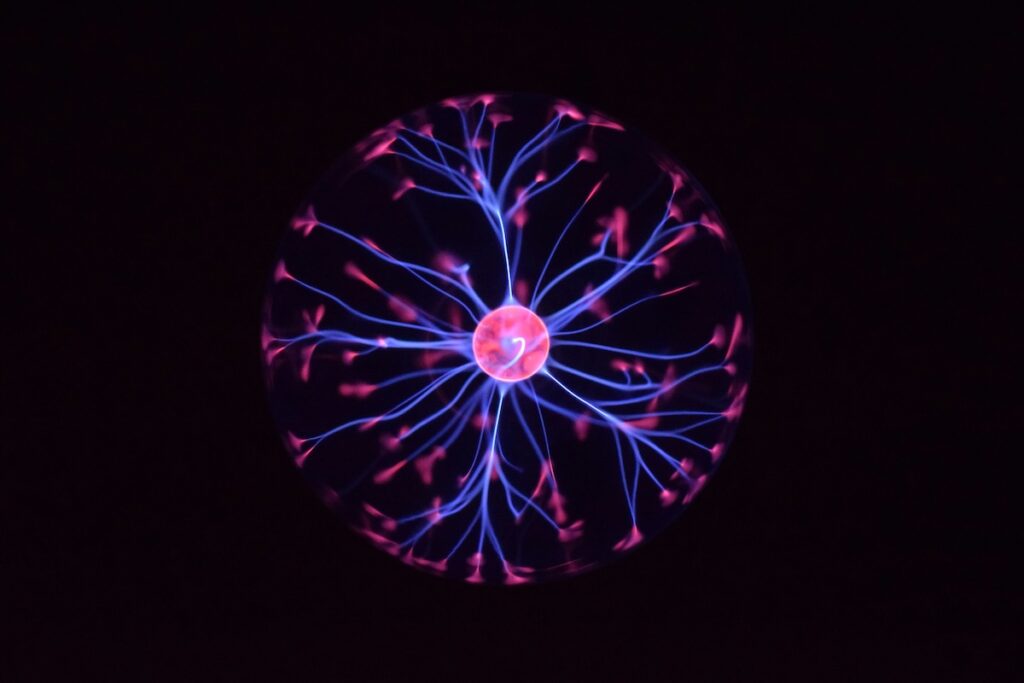
いかにして消費者が顧客になるか?
6つの認知と消費者が顧客になるプロセス
商品やサービスを知らない人が「欲しい!」「買おう!」と行動するまでには、段階的な「認知のプロセス」が働いています。これは心理学の基本的な認知機能と深くつながっています。
まずは「存在を知る」ことから始まります。人は五感を使ってブランドや商品を認識します。例えば、街で看板を見かける、SNSの広告を目にする、友達が使っているのを聞くなどです。知覚認知は、最初のきっかけです。五感での認知がないと購買行動は基本的に始まりません。
知覚認知の次に、数ある情報の中からその商品に「注目」する段階が必要になります。例えば、スマホ広告の中で自分の趣味に合う商品に目を止めるというのが注意認知です。消費者は「気になる」状態 になることで、情報が記憶に残る可能性が生まれます。
知覚認知、注意認知を経て、消費者に一度触れた情報が、消費者の頭の中に残るかどうかがブランドの分かれ目です。例えば、友達の話や体験談を覚えていて、買い物のときに思い出すというのは記憶認知が作用している状態です。ブランドは、消費者の記憶に残らないと、次の行動(比較・検討)につなげられません。
言葉や文章で商品の特徴を理解する段階では多くの場合で言語認知が必要になります。例えば、Webサイトで「このシャンプーは髪に優しい」と説明を読むことが言語認知です。なんとなくイメージしていた良い印象が言葉になっている状態を整えます。消費者は言語化された情報を通じて、「自分に必要かどうか」を整理しやすくなります。
記憶認知や言語認知を通じた理解をもとに「私に必要?」「本当に買うか?」を考える段階が思考認知です。例えば、他の商品と値段・機能を比べる消費者、口コミを参考にする消費者、家族に相談する消費者は思考認知を働かせています。思考認知によって、最終的な購買の意思決定が行われます。
メタ認知プロセスでは、「自分の判断が正しいか?」を客観的に見直す段階です。例えば、「安さだけで選んで後悔しないかな?」「長期的に使えるか?」「衝動買いではないか?」などと購入を決断する前にふり返る段階です。消費者は、メタ認知を働かせることで、衝動買いではなく納得感のある購入に至ります。
認知の流れは顧客になる流れ
認知の流れ=顧客になる流れ
消費者の中で、6つの認知が順番に機能することで、消費者は「ただの通行人」から「顧客」へと変わっていきます。認知戦略とは、知ってもらうだけではなく、注意してもらう、記憶に残すという先の認知を考慮することが重要です。
知覚認知 … 商品に気づく
注意認知 … 興味をもつ
記憶認知 … 覚えておく
言語認知 … 理解する
思考認知 … 比較して判断する
メタ認知 … 自分の判断を見直す