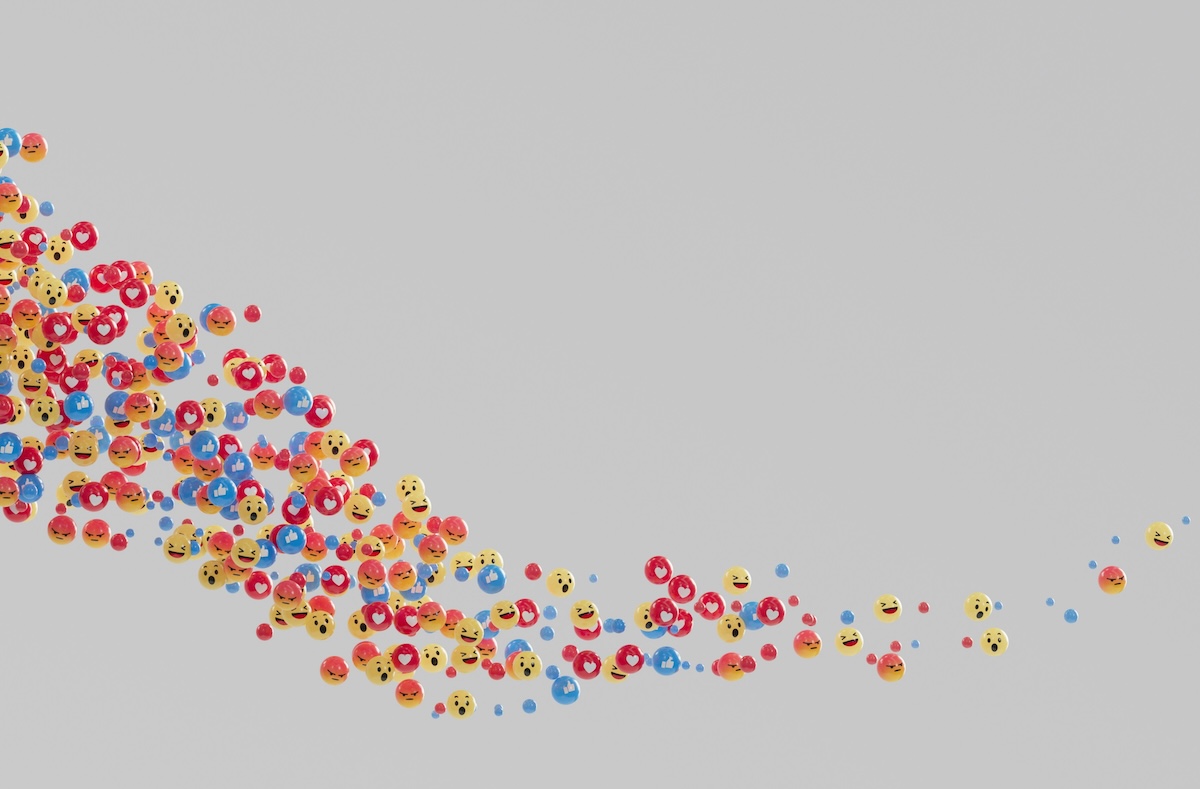株式会社SHISEILABO 代表取締役兼CMOの武山です。今回は、プロジェクトのスタートとゴールについて考えてみました。私たちのプロジェクトマネジメントでは、どの期間にどこまでやるか?は1日ごとに決めるという鉄則があります。
プロジェクトマネジメントでは、多くの場合「年間計画」や「半年計画」から始めます。しかし、実際の成果は短い期間での着実な進捗管理から生まれます。今回は「スタート」と「ゴール」の設定方法と、期間管理の考え方についてお話しします。
この世界は全てがプロジェクトまたは物語として機能しています。

全ての期間は短い方が良い理由
当たり前のことをお伝えしますが、設定期間が長すぎると、予測できない未来が増えるので色々な不都合が生じます。例えば、ゴールまでの距離感がぼやける、優先順位が変わってしまう、モチベーションの波が大きくなるなど。
一方で、短い期間で区切ると、成果が見えやすくなり、修正もしやすくなります。特にビジネスでは「小さく区切って素早く修正」することが成功確率を高めます。
ロードマップと単月計画の2つが大切
プロジェクトで何をマネジメントするか?
プロジェクトや事業を進める上では、ロードマップと単月計画の並行利用がおすすめです
ロードマップはプロジェクトの全体像とさらに細分化したものです。3ヶ月以上のスパンで作成し、目的としては参加者で認識を合わせる方向性の確認に使います。大きなマイルストーン(製品リリース、イベント開催など)を明示するのはロードマップです。
一方、単月計画は実行計画になります。タスクレベルで情報を落とし込み、日々の動きと連動させることが大切です。月単位で振り返り、翌月の修正に反映することで精度を高めていきます。
この2段構えがあれば、「長期戦略」と「日々の実務」をつなぐことができます。

理想のゴール設定
理想的なゴール設定について考えてみたいと思います。定性目標の重要性については以前触れていますので下記の記事も参考にしてみてください。ここでは、プロジェクト単位のゴール設定について触れてみます。
ゴール設定で最初に考える大切なポイントは『具体的で測定可能かどうか?』ということです。例えば、契約件数◯件、売上◯万円など達成することで実益になるなどなぜ?という部分に触れることが重要です。
次に、期限を明確にすることです。例えば、◯月末までに達成するなどの具体的な期限を決めます。そして最後に重要なポイントは、達成後の状態がイメージできることです。参加者やチーム、顧客、市場の変化まで想像できれば最高です。
ゴールは数字だけでなく、その達成がどんな意味を持つかまで定義しておくと、チーム全員が同じ方向を向けます。
理想のスタート
続いては理想のスタートについて考えてみたいと思います。スタートはただ始める日ではなく、戦闘態勢に入る日と考えると成功率が上がります。
スタート時に現状の立ち位置を明確化することが大切です。その際には過去のデータから現在地を把握すること、課題やリソースを把握することが大切です。
初動の「加速期間」を設定します。全てのプロジェクトで最初の1週間で勢いを作ることができれば、基本的にうまくいく確率はとても高いです。チーム全員が「なぜこのプロジェクトをやるのか」を理解している状態でスタートを切りましょう。

1年間は365分割されている
1年=365日。
日ごとに小さなゴールと小さなスタートを設定すれば、年間365回の改善サイクルが回せます。
毎日のスタートで今日やることを明確化します。そして、毎日のゴールで達成度を振り返り、翌日に反映します。この基本的でシンプルな考え方がベースにあるプロジェクトはとても魅力的です。
年間計画が失敗する最大の理由は「1年を1単位」で見てしまうこと。1日ごとの積み重ねこそが長期計画を実現します。
着想と計画が大切
着想(アイデア)だけでは形になりません。また、計画だけでは動きが鈍り、なぜやるか?という部分が欠けてしまいます。
着想→計画→実行→修正のサイクルを短期間で回すことが鍵です。
SHISEILABOでは、「最短1日単位」で進捗を測る仕組み」をプロジェクトに組み込み、長期目標をブレずに達成しています。

まとめ
全ての期間は短く区切るほど成果が出やすいということがお伝えできれば幸いです。3ヶ月以上のロードマップは方向確認用、単月計画は実行用として並行利用しましょう。
ゴールとスタートは具体的かつチーム全員で共有し、1日ごとの小さな達成が大きな成果をつくります。
「今日やること」を決めて動き出すことが、未来の成果を確実に引き寄せます。この世界は全てがプロジェクトまたは物語として機能しています。