株式会社シセイラボCMOの武山です。本日は、「価格弾力性」について触れてみたいと思います。当社ではすべてのビジネスに対して、小売販売とアートプロジェクトを対極に置いた考え方の中で考察し、創造的思考を用いて新たなビジネス機会を提供しています。
今回のテーマである価格弾力性とは「価格が変動したときに需要がどれだけ変化するか」を示す指標です。アートブランドでコストから価格設定する間違いを明確にする目的もあります。
小売販売×価格弾力性の基本
まずは、小売販売の価格弾力性に触れてみます。生活必需品や日常消費財は、一般的に価格が上がると需要が下がりやすい傾向があります。高すぎると買いづらいというイメージです。この場合、「価格弾力性が高い」という表現をします。
特に、競合商品が多いカテゴリーでは、消費者は簡単に代替品を選べるため、価格競争が激化します。例えば、スーパーでの牛乳や卵は価格が数十円違えば別の商品に切り替える消費者が多い傾向があります。
アートブランド×価格弾力性の基本
小売販売に対して、アートプロジェクトの場合はどうでしょうか?アートプロジェクトの場合、作品や体験の独自性が強く、顧客にとって基本的にそれ以外の代わりがありません。つまり、代替不可能性が高いのがアートプロジェクトです。この場合、価格を上げても需要が大きく落ちにくい「非弾力的」な側面を持ちます。ただし、市場規模や購入者層(コレクター、ファン、投資家など)が限定的であるため、需要の総量自体は小売と比べると脆弱です。つまり、「好きな人にだけ刺さる」というイメージです。例えば、あるアーティストの作品を「欲しい」と思うのはコレクターやファンなど特定層に限られます。
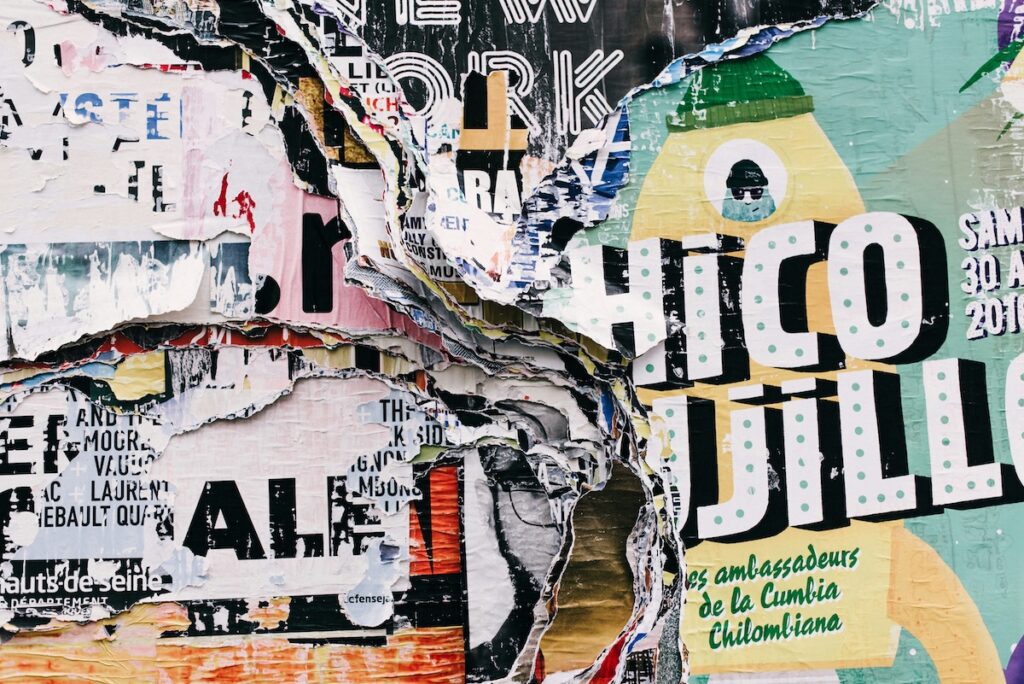
ブランドの好きを支える3つの要素
ここで、「ブランドの好き」を支える3つの要素を紹介します。要素はこの3つだけです。
ブランド、商品、サービスの顧客からの好意度を支える3つの要素は「価格」「ブランドエクイティ」「機能」です。価格弾力性が高い小売販売の場合、基本的に機能は同程度、価格は近似値となります。そこで、小売販売、アートプロジェクトに共通する最も重要な要素が「ブランドエクイティ」になります。
ブランドエクイティの役割
Google広告投資における認知の獲得(認知率最大100%)や流通網の強化などによる配荷率(最大100%)の向上などブランドを支える要素とは別に顧客からの好意度をささえる最もたるブランドエクイティについて触れていきます。
小売販売
小売販売のブランドエクイティ領域では信頼性や知名度が顧客からの相対的な好意度を獲得し購買を後押しします。ブランド力が高い、つまり広く認知されており、比較的入手しやすい状態で、顧客からの相対的好意度も高い状態では、価格プレミアム(同じ商品カテゴリーでも高値で選ばれる)が成立し、価格弾力性を抑える効果があります。例えば、無地の白いTシャツでも、ユニクロと無印良品、ノーブランドでは価格差は歴然です。
小売販売では、「ブランド力」が選択を支えます。
アートプロジェクト
一方で、アートプロジェクトにおけるブランドエクイティ領域では、作家名やプロジェクトのコンセプト、文化的背景、社会的意義が「唯一無二の価値」として作用します。ブランドエクイティが高いほど「市場価格」ではなく「象徴的価値」で取引され、価格弾力性は極端に低下します。アートにおいては「ブランド=作者やプロジェクトそのもの」であり、販売価格は市場原理よりも文化的評価やストーリーテリングに依存するのです。

小売とアートを対極に置く意味とは?
小売業界とアート業界を対極に置く考え方の論点を3つの観点で整理してみます。
1つ目の観点は「需要特性」です。小売ブランドの場合は大量消費型で価格弾力性が高く、アートブランドの場合はニッチ市場に分類され価格弾力性が低いと捉えることができます。
2つ目の観点は「ブランドの役割」です。小売ブランドは差別化が必須で、価格維持の武器が必要になります。価格維持の武器になる要素は企業や環境により刻一刻と変化します。一方で、アートブランドの役割は市場形成そのものです。
最後に3つ目の観点は、「価格と価値の関係性」です。小売ブランドは基本的には安い方が選ばれやすく、高いと選ばれにくいという傾向があります。一方で、アートブランドの場合は価格や値段が高いほど文化的価値が認められる場合があり、ブランドが確立すると、価格が価値の指標になる逆転現象が起こります。
このように、小売ブランドとアートブランドを対極に捉えて市場構造を理解することで、自社の次の一手を見極めるという理論が今回のテーマです。

対極的な戦略デザインの方向性
このように、小売ブランドとアートブランドを対極に据えることで見えてくる戦略の基本的な違いもあります。
小売ブランドでは「価格×量の最適化」が鍵です。つまり、すべきことは比較的明確で、広告やプロモーションを実施し、価格調整で需要を操作し利益の最大化を図る戦略が基本になります。
一方で、アートブランドでは「ブランドの象徴性強化」が鍵になります。コンセプト、扱うテーマ、ストーリー、文化的意義、社会的メッセージが価格設定を支えます。
顧客視点のシンプルな整理では、小売ブランドは「消費のための選択肢」、アートは「意味のための投資や体験」です。その違いを理解し前提とした上で、ブランドエクイティ構築のアプローチを変える必要があるのです。
まとめ
今回は「小売ブランドとアートブランドから見る価格弾力性」について触れてみました。小売販売においてブランドエクイティは価格競争を和らげる役割を持つのに対し、アートプロジェクトではブランドエクイティが市場そのものを創出し、価格弾力性を事実上無効化する力を持つ、ということがご理解いただけたでしょうか?
最後に、現代の消費市場とアート市場の違いについて整理してみましたのでご参考ください。対極的思考はどの業界でも役にたつ視点です。本日もご覧いただきましてありがとうございました。
消費市場(小売販売)
- 大量生産・大量消費が前提
- 価格や利便性で比較され、競争が激しい
- 消費者は「必要性」や「コストパフォーマンス」で購入を決定
- 価格が需要に直結するため、価格弾力性が高い
アート市場
- 独自性・希少性・文化的背景が価値を決定
- 代替が効かず「唯一無二」であることが重要
- 購入者は「美的満足」「文化的意義」「投資価値」で購入を決定
- 価格よりもブランドや象徴性が需要を左右し、価格弾力性は低い
