本日のブログは『AI時代のネガティブケイパビリティ』というタイトルでお伝えします。
情報は『足りない』から『多すぎる』時代となりました。正解が瞬時に提示されるほど、私たちは判断の難しさと向き合うことになります。そこで鍵になるのが、ネガティブケイパビリティ(Negative Capability)という概念です。
ネガティブケイパビリティとは、「すぐに答えを出さず、不確実さや曖昧さに耐えながら問いを持ち続ける力」です。AIが「もっともらしい答え」を量産する時代に、人間の競争力は『すぐ決めない』という高度な態度に宿ります。
ネガティブケイパビリティとは何か
ネガティブケイパビリティは、もともと詩人ジョン・キーツ(イギリスのロマン主義の詩人 1795年-1821年)が提唱した概念で、「不確実・神秘・疑念の中に、性急に理由づけしようとせず留まる力」を指します。
ビジネスに置き換えれば、断片的なデータや相反する意見を前に、すぐに結論へ飛ばず、観察・熟考・小さな実験を繰り返しながら最適な『次の一歩』を選ぶ能力と捉えられます。




インターネットがなかった時代
インターネットがなかった時代のネガティブケイパビリティ
インターネットがなかった時代は、情報を取得する場所も生活圏と関係土地からに限定され、情報入手には多くの時間がかかっていました。そのような時代では、否応なく『待つ力』や『現地現物』が鍛えられていました。
今でもスマホを持たずに旅をするバックパッカーはいるのでしょうか?
『待つ』という行為がビジネスに与える影響は時間以外にもあるようです。例えば、メールのない時代では、商談を終えた営業マンは返答をどのように受け取っていたのでしょうか?
結果はすぐに結論付くことは少なく、例えば一晩持ち帰り、翌日手紙で返答するみたいな時代があったのは事実です。すぐに結論づけることがない時代の、『冷却時間』がより高度な意思決定の質やコミュニケーションを担保していたのかもしれません。
また、現場観察が全ての時代では、データや資料よりも実物を見ることが当たり前であったことでしょう。対峙するものに『希少性』すらあるため、どうしても5感をフル活用する必要がありました。五感は『ノイズ除去装置』としても機能していたことでしょう。
さらに、適度な情報環境では、自然と仮説が熟成されます。短期の揺らぎに引きずられない環境が当たり前だったことでしょう。このように『不便さ』が、結果としてネガティブケイパビリティを自然に育てていたとも言えます。
SNS時代
SNSがカルチャーになってからのネガティブケイパビリティ
FacebookやTwitter(現行のX)やInstagramなどのSNSは速度・可視性・同調圧力を一気に高めました。コンテンツの評価が数字で見える世界は便利かもしれませんが、短期的なトレンドがカルチャーとなる確率は極めて低く、短期の反応に経営がジャックされやすい時代です。
このような時代においては『反応しない力』(炎上予防と同時に熟考の余白を守る設計など)が重要になります。また、概念的なイメージにはなりますが、SNSを相手にする場合は、即時レス、広報を担うフロントと観察力を責任する熟考・検証を担うバックに分ける、2層運転のチーム戦が有効かもしれません。
SNSが一つのカルチャーとして存在することは否めませんが、短期的なトレンド的な声と長期の価値を明確に仕分けることが重要です。コメントやバズは可視化が容易であたかも『波に乗っている企業・ブランド』のように見えるかもしれません。しかし、ビジネスは顧客が中心です。LTVやブランド信頼は遅行・不可視なものですが、両者のバランス設計が肝となります。「いま決めない」ことを、怠慢ではなく戦略として扱えるかが問われます。
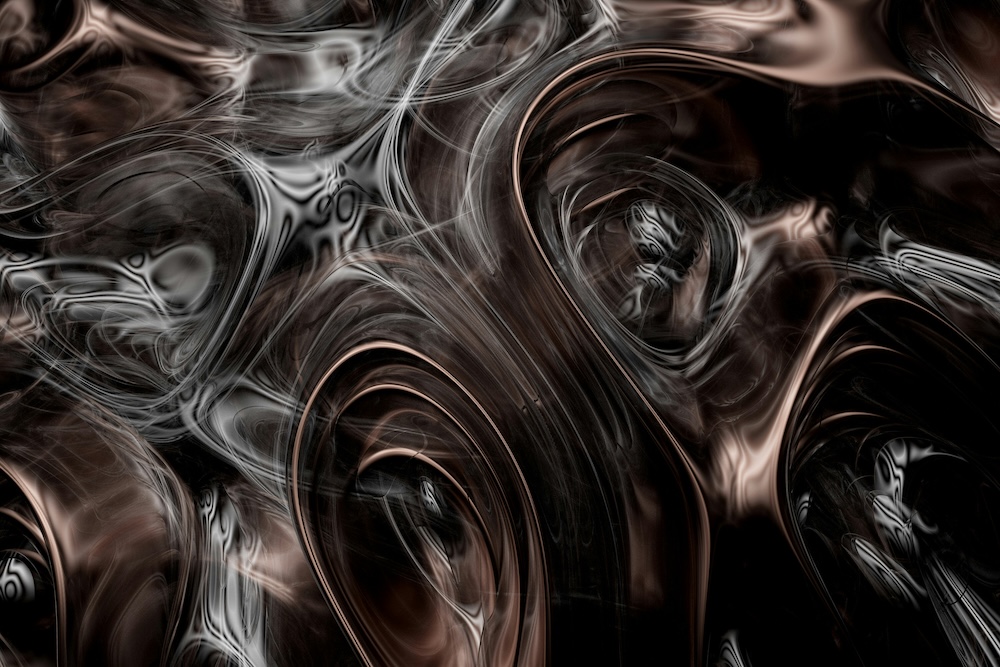
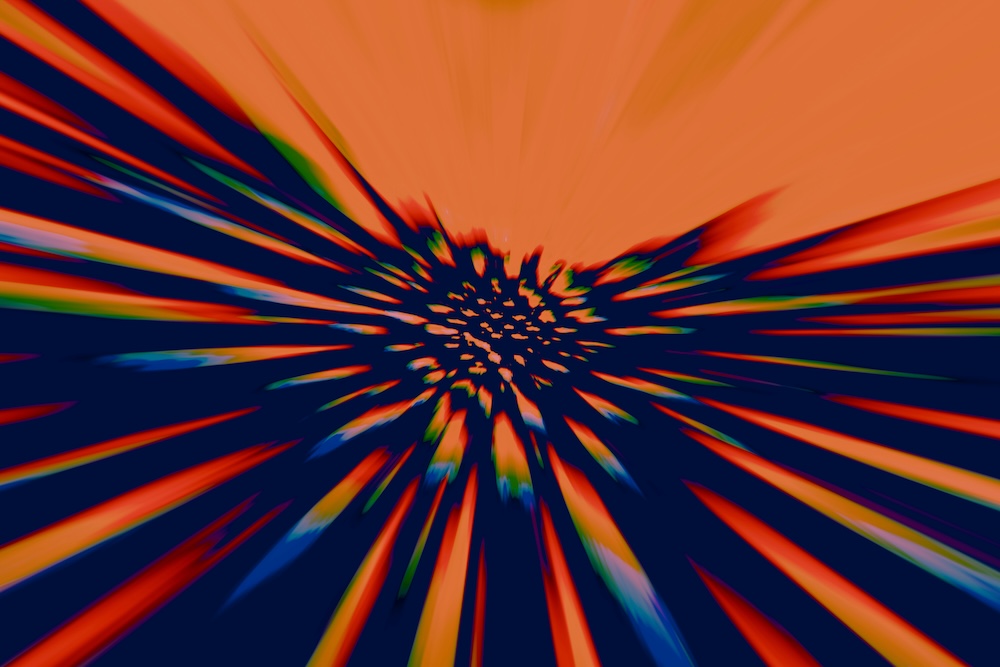
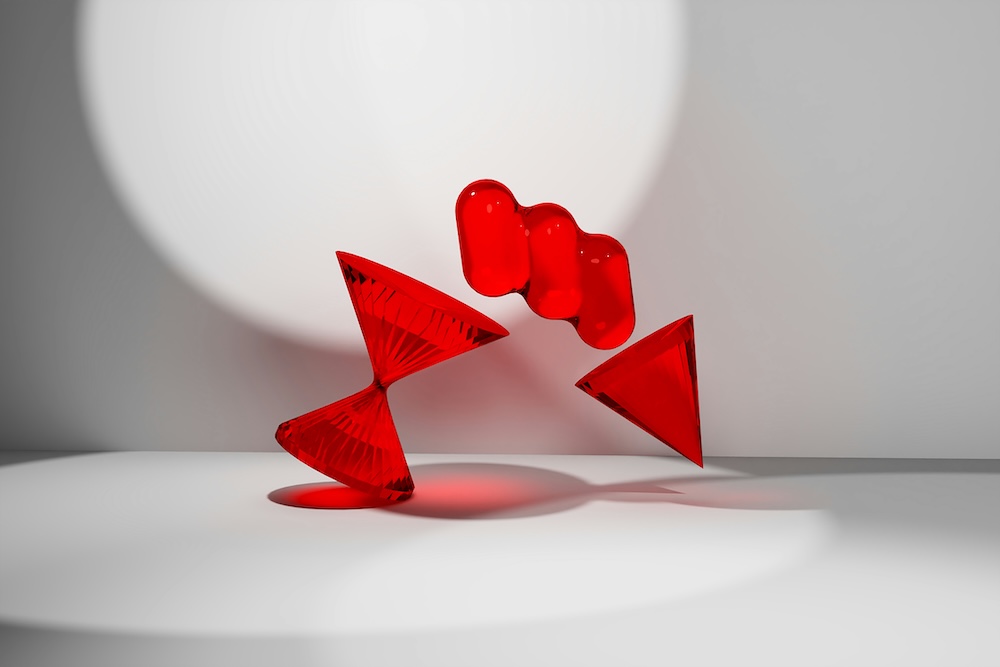
なぜAI時代に重要なのか?
例えば生成AIは平均化・要約・最適化に優れ、『正解っぽさ』の供給量を最大化しています。
私たちは生成AI時代を直視しなければなりません。不完全なデータや設計バイアスがもっともらしく拡張される誤差の増幅、誰もが同じ正解に到達し、創造の核心(違和感や未定義領域)が削がれる差別化の希薄化、AIが出した答えに飛びつくほど、コモディティ化の坂を転げ落ちていることに。
そんなAI時代の現実に、ここで効くのがネガティブケイパビリティです。「まだ決めない」「観察を続ける」「小さく試す」を、AI時代の標準装備にすることで、人間の審美眼・文脈理解・価値判断が生きてくると思いませんか?
おすすめのフレーム
『SHISEILABO式』のネガティブケイパビリティ実装フレームを提案してみます。ご提案するフレームは、探索、保留、意味づけ、小決断、学習の順番です。探索のExplore、保留のSuspend、意味づけのMeaning、小決断のSmall Commit、学習のLearnから名前をつけようかと思いましたが良い名前は思いついていません。
まずは、探索をスタートにします。探索ステップはシンプルで、一次情報を取りに行くというものです。現場・顧客・ログの生の摩擦に触れることが重要です。次に、重要判断には短くても一晩の冷却時間を設けます。これが保留のステップです。
続けて、保留させた一次情報から相反する事実を同時に成立させる仮説を並行で保持します。これが意味づけのステップです。意味づけを終えた段階でN=10〜30の小さな実験で検証します。失敗は安く、学びは濃くというイメージを持った小決断のステップです。小決断の先には学習ステップがあります。得られた結果を問い直し、再び探索のステップを繰り返してみます。
重要なことは『答えのない』未解のまま保留し続けることを善とするということです。
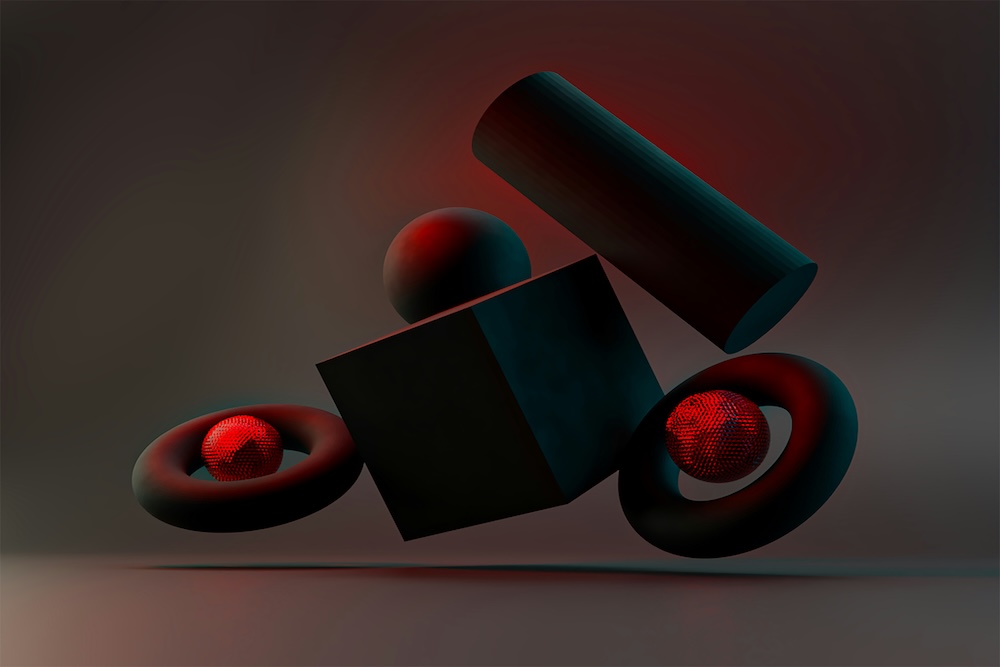

ネガティブケイパビリティ10項目提案
実際のビジネスにおいて、ネガティブケイパビリティを活用してみます。例としていくつか挙げてみました。
翌朝チェックルール
例えば、夜に書いたSNS投稿、広告案、広報文は朝に再読するルール(経営者向け)
問いのバックログ運用
意思決定を『保留した理由』と『再検討日』を記録するルール
するしないカレンダー運用
「判断する・決める日」と「保留する・熟す日」を分けて予定化するルール
反証プロンプト習慣
生成AIで『反対仮説』の生成を習慣化(例えば「この案が失敗する理由を3つ」)
欠測の可視化
例えばデータの可視化において『取れていないデータ』の欄を設けてみます。無い情報が最大のリスクであることを可視化する別の価値も。
3つの速度帯
情報の受付を『秒管理』熟考期間を『日管理』学習期間を『週管理』で運用するルール
KBI運用ルール
KPIに加えて行動ベースのKBI1(観察回数、顧客インタビュー数等)を設定
撤退の美学
戦略策定時や実験前にExit条件と継続条件を書き出すルールを運用
未決ログ資産化
未決事項を組織やチームで見える化します。焦りの共有を減らす目的
SNS時代の心得
組織をマネジメントする役割を持っている場合、現場の情報との距離の設計も重要です。例えば、担当者以外に『見えすぎる』状態を避けて心理的トリガーを減らす目的で、通知を再設計してみます。また、GoogleレビューやAmazonレビューなどは意見(価値判断)と事実(体験報告)を分けて記録することで、ただ読むよりもストレスを軽減することができます。
マネージャーが率先して『まだ決めない』という態度をカルチャーにすることで、情報が溢れるスピード感のありすぎる時代にチームの焦燥を鎮め、顧客の信頼を積み上げるカルチャーを醸成できるのではないでしょうか?
最後に
不確実さを『許容できる』ことが、AI時代の優位性になる
ということをお伝えできればと思います。AIは簡単に答え合わせをしてくれます。また、スムーズな回答は、答える文化を早めます。そのような環境にあって、『だからこそ人は問いを深める。』という態度が差別化につながりそうです。
決断の速度だけでは、同質化の波に飲まれます。『まだ決めない』を戦略化すること、これこそが、AI時代の経営と現場におけるネガティブケイパビリティの本質と言えるのではないでしょうか?
まずは重要な発信は一晩寝かせましょう。『すぐ決めない』を、価値創造の作法に。SHISEILABOは、その作法を設計し、現場で機能させる伴走を続けていきます。
- KBIは重要行動指標(Key Behavior Indicator):目標達成(KPI)のために、具体的な行動につながるように設定される指標 ↩︎